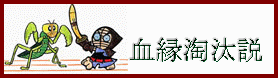
「生物は種族を維持・繁栄させることに生存理由がある。」1964年、当時ロンドン大学の大学院生であったハミルトン(W.D.Hamilton)によって、こうした“定説”を覆す画期的な理論が提唱された。
ダーウィンが『種の起源』の中で投げかけた、働きバチが自らは直接生殖に関与しないのに、一族のために働くという「利他的」な性質がどうして子孫に伝わるのかという疑問に対して、100年以上を経てハミルトンが集団遺伝学の見地から新しい「血縁淘汰(選択説)」を提唱したのである。簡単にいえば、この「他を利すために働く」行為によって、自分と同じ遺伝子を持つ血縁者である女王バチが多くの子供を残せば、このような利他的な性質の遺伝子もまた子孫に継承されるという理論である。いいかえれば、動物は同じ種族でも血縁関係のない非社会性の個体間で、自分の子供を減らしてほかの個体の子供を増やすようなことはないというわけである。 今日ハミルトンの理論によって、生物学は新しい局面を迎えている。そして初めて動物の社会生活の進化を量的にとらえることが可能になり、「社会生物学」とよばれる今をときめく新分野が誕生した。それは血縁の度合いを数学的に解析することを含めて、進化学の上にも大きな一石を投じることとなった。そして冒頭の言葉も1970年代から、「動物はそれぞれの個体が自分の遺伝子を持った子孫をより多く残すために生きている」と解釈がまったく変ってきた。 つまり、仲間のほかの個体のことなどはどうでもよく、要はそうした仲間を蹴落としても自分自身の遺伝子さえ残せればいいというわけである。 まだこうした考えで動物の進化や行動がすべて解決されているわけではないが、オスが先夫の子供を殺してメスに自分の子を産ませる多くの類人猿、生んであるほかのオスの卵を破壊する鳥たち、メスの体内からほかのオスの精子を掻き出すトンボなど、およそ種族維持に矛盾する行為はこれで説明できる。 こうなれば動物のそれぞれの個体はずいぶん利己的な存在にみえるが、これも違う。そうした行為をつかさどっているのはあくまでも遺伝子であり、動物は利己的な遺伝子の生存機械として利用されているに過ぎないという。おのおのがた、ご安心召されい。無責任なのも、酒癖が悪いのも、あなたがいたらぬためではない。みんな遺伝子が勝手すぎるのだ。 [研究ジャーナル,17巻・3号(1994)] |
もくじ 前 へ 次 へ
