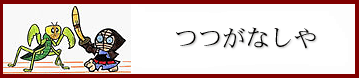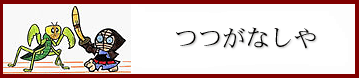※クリックすると大きな画像を
ご覧になれます |
 |
アカツツガムシの成体
(全国農村教育協会原図) |
新潟・秋田・山形県の大きな河川の下流地帯に古くから恐ろしい風土病があった。夏のある日突然高熱を発し、3週間ほどで死に至る奇病で、かつてその死亡率は40%内外にも達した。
河川敷の芦原を開墾して畑を作る貧しい農家の人々が多く犠牲になり、河川熱あるいは洪水の頻発地帯なので洪水熱とも呼ばれていた。
そして、これがアカツツガムシ(赤恙虫)という微小なダニの幼虫によって感染することが田中敬助によって明らかにされたのは1899年のことである。さらに日本の医学者たちの努力によって、
1930年にはその病原体が新種のリケッチャであることが判明した。アカツツガムシは幼虫期だけネズミや鳥や人などの温血動物から吸血し、成虫から卵を経由してリケッチャを受け継いだ保毒虫が感染を起こす。
またこの研究が契機になって、伊豆七島の「七島熱」、房総半島の「二十日熱」、高知の「ほっぱん」など、軽症ながら原因不明の風土病も、タテツツガムシやフトゲツツガムシの媒介する新型の恙虫病であることがわかった。
こうした一連の日本の研究は、世界各地の恙虫病の解明に大きな足跡を残し、世界的な評価を得ている。
ツツガムシ類は、ネズミを主寄主として原野に発生するため防除が困難で、現在でも年によっては地域的にかなりの数の患者が発生している。しかし戦後、恙虫病に卓効を示すテトラサイクリン系の抗生物質が発見され、
日本では1950年代以降、恙虫病による死亡者は記録上ゼロになって現在に至っている。
手紙の冒頭の「貴殿にはつつがなく……」、小学校唱歌『故郷(ふるさと)』の一節「恙なしや友がき」。
その「つつがなし」は「ツツガムシがいない」の意味だ、という話をぼくは若いころだれかに聞き、脳の奥深くにインプットされてしまった。以来半世紀、物知り顔で何度か知人にも受け売りしてきた。
"つつが"とは"やまい"の古語で、用例は9世紀にさかのぼる。ツツガムシの名も「病気を起こす虫」の意味であるが、その事実が判明したのは19世紀末である。考えれば(考えなくても)ツツガムシが「つつがなし」の語源になるはずがない。
ぼくの話を感心して聞いてくれた多くの知人に、この場を借りてつつしんでおわびしたい。
ただ、いまは「つつがなし」そのものがすでに死語になりつつある。しかし、汚染地で釣りなどをした1〜2週間後に、もし原因不明の高熱が続いたら、一応「つつがあり」を疑った方がいい。
いくら特効薬があっても、恙虫病を見たこともない医者に風邪と誤診されたら、久びさの死亡例になる恐れがある。
[研究ジャーナル,25巻・2 号(2002)]
|