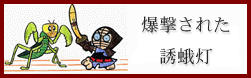
|
先日岐阜の友人から『岐阜県農業技術研究所100周年記念誌』をいただいた。公立の農業試験場も相次いで百周年を迎えたのは慶賀の至りで、
こうした記念誌はまた歴史に埋もれたエピソードを再発掘する意味でも興味深い。この記念誌にも、山田忠行氏が寄せた思い出にこんな記録が出ていた。
岐阜県農業技術研究所(当時、県立農事試験場)は今こそ周囲が市街化され、往時の面影はないが、戦時中までは「田圃と畠の真ん中にポツンと本館が建っており、 雪の夜は、野狐が場内を走り回っていた」という場所であった。 山田氏は昭和20年の4月に試験場に採用、翌月徴兵され、8月に終戦、再び試験場に復帰した経歴を持たれる。「当時片田舎だった試験場も焼夷弾で丸焼け」 「私の復帰した種芸部の試験田も、水稲が立毛のまま焼けただれ見るも無残な姿」だった由である。では、こんな”野中の一軒家”がなぜ攻撃されたのであろうか。 それは「空襲警報発令中下は研究用の誘蛾灯を消灯させられたが、ある晩、担当者が消灯せずに避難したため、米軍機の格好の目標となり、 約370数発が投下され、農試本館と付属施設が一瞬のうちに炎上し、明治以降の貴重な研究文献・成績原簿類のすべてが灰燼に帰した」とある。 実に終戦1か月前の事件であった。 また、山田氏は徴兵を前に、「1日でも早く戦列に加わるべく、赤い血潮が燃えたぎっていた」とも述懐している。 同じ時代を共有したわれわれの世代でなければ、こうした話は通じないかもしれない。また、われわれにとってもかつて経験したはずのこの時代のことは、 風化が進み、思い出すことすら少なくなった。が、ときにこうした話に出会うと、蛍光灯を一晩中消さずに済むこの時代の永続をつくづく願わずにはいられない。 |
|
[研究ジャーナル,25巻・7号(2002)]
|
もくじ 前 へ 次 へ