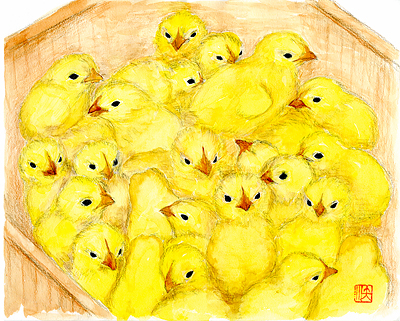
【絵:後藤 泱子】
(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)
|
わが国の鶏卵消費量は、業務用も含めて年間1人当たり330個ほど。欧米諸国が260個前後なのに比べて、格別に多い。まさに世界一の鶏卵王国と誇りたいところだが、その種鶏のほぼ93%を海外の業者に依存していると聞いて、がっくりした。
ここで種鶏について説明しておこう。私たちの食卓にのぼる卵を産む鶏は実用鶏。その実用鶏は、ふつう3元ないし4元交配雑種であり、その親を種鶏、種鶏の親を原種鶏とよぶ。つまり種鶏・原種鶏の改良こそが近代養鶏の首根っこなのだが、
その首根っこを「青い眼の鶏」に握られているというわけだ。
こうした状況に、わが国の種鶏がおかれるようになったのは、昭和37年(1962)のひな鶏の自由化以来だろう。ちょうど規模拡大が急進した時期だが、国産種鶏はこの流れについていけなかった。
戦中戦後、古典的なメンデル遺伝に固執し、産卵数抜群の優良鶏はつくったが、多羽飼育に向かず、群としての安定生産性でおくれをとったからである。当時、海外では、雑種強勢をねらった複交配育種が主流で、
強健性・斉一性に富み、飼料効率など経済性にもすぐれた種鶏が、すでに広く出回っていた。国内の孵卵業者が海外種鶏になびいたのは、ある意味で仕方のないことだった。
だがそんな大勢に抗し、国産種鶏の孤塁を守ってきた育種家がいる。後藤静一と彼がひきいる後藤孵卵場(岐阜市)である。
静一が育種に手を染めたのは昭和14年(1939)、37歳のときであった。はじめは近くの養鶏会社に勤めていたが、やがて独立、以後83歳で亡くなるまでの40数年、国産種鶏の改良に生涯を捧げている。
静一がとくに意を注いだのは、新技術の導入だった。昭和10年代(1930年代後半)には、すでに実用化していた蚕のハイブリッド品種に学び、名古屋種・白色レグホーンの一代雑種「名白」を育成している。
今日のハイブリッド時代の先駆となったトウモロコシの一代雑種がアメリカで世に出る前、養鶏でも一代雑種は邪道扱いされていた時代のことである。研究熱心な彼は、あえてタブーに挑戦したのだった。
後藤の種鶏を今日の地位に押し上げたのは、なんといっても集団育種技術の導入だろう。メンデル遺伝学をさらに生物集団を対象に発展させた育種法だが、わが国で本格的に注目されるようになったのは、
戦後になってからであった。後藤はこれをいち早く導入、種鶏改良の現場に適用している。導入の橋渡しをしたのは、静一の長男静彦だった。
昭和27年(1952)、アメリカに留学した静彦は、ここで最新の集団遺伝学に接して、これを習得、3年後に帰国する。ついで静彦の弟悦男もアイオワ州立大学に留学、
さらに新知識を吸収して帰国、同社の育種体制は格段と厚みを増していった。後藤の強みは海外研究との太いパイプをもっていることだろう。現在もアイオワ州立大学などと交流をつづけている。
そうした進取の気風が、同社の主力商品、交配種「さくら」、赤玉鶏「もみじ」の開発につながったのだろう。最近の採卵鶏の調査では、国内種鶏のシェアはおよそ7%、そのほとんどを後藤孵卵場の種鶏が占めている。
「日本に適した鶏は日本人の手で、日本の気候風土の中から生まれなくてはならない」とは、海外種鶏に戦いを挑んだときの静一の言葉である。日本の農業技術者すべてが心に刻んでおきたい言葉である。
|