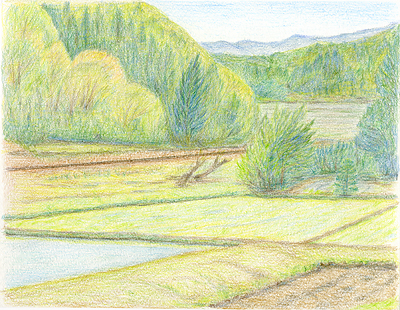
【絵:後藤 泱子】
(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)
|
平成2年(1994)に、本欄「日本の農を拓いた先人たち」を書きはじめて、17年になる。最初は10回もつづけばと思っていたが、途中2度の中断をはさんで、今回でなんと151回に達した。このあたりで筆を置こうと思う。
長い間愛読いただいた読者と、貴重な紙面を割いてくださった共済新聞に心から感謝申し上げる。
17年前に、この欄を書きはじめた動機は(1)日本農業の節目節目で、技術がいかに大きな役割を果たしてきたか、そして(2)その技術の多くが、ほかならぬ農家自身の手で創りあげられたことを、
読者の農家自身に知って貰いたいというところにあった。
戦後の食糧難に、もし長野県の農家荻原豊次が考案した「保温折衷苗代」がなかったら、飢餓はさらに深刻だったに違いない。
もし周辺農家の熱望に応えて、長野県農試飯山試験地の松田順次(まつだじゅんじ)技師が「室内育苗」を開発することがなかったら、稚苗田植機の誕生はもっと遅れただろう。貿易自由化の嵐が荒れ狂うさなか、山形県の佐藤栄助がつくったサクランボ「佐藤錦」、奈良県の刀根淑民のカキ「刀根早生」、和歌山県南部川村の「南高ウメ」がなかったら。地域農業は今以上に苦境に立たされていたに違いない。
執筆の後半は、さらに(3)技術を縁の下で支えた人びとに光を当てることを心がけた。世界屈指の多収・良質を誇るわが国水稲品種も、もとは明治時代の農家が見出した「神力」
「旭」「愛国」「「亀ノ尾」などの優良品種があって、
はじめて達成できたことを。また今日、日本中の食卓をにぎわしている節成キュウリも、埼玉県の関野茂七らの
「落合節成」があって育成できたことを、ぜひ知ってほしいと思ったからである。
最後に、連載執筆後に明らかになった2つの史実を追加・修正しておこう。
ひとつは水稲「愛国」発祥の地についてである。「コシヒカリ」など、現在の品種のほとんどがその品種の血を引く「愛国」は、これまで発祥地が不明の品種とされてきた。だが最近、宮城県古川農業試験場の佐々木武彦元場長の努力で、
この品種が宮城県舘矢間村(現在の丸森町)の蚕種業本多三学が取り寄せた伊豆の種子に由来することが特定できた。5月には記念碑の建立が予定されている。
もう一つは、長野県特産のエノキタケの創始者についてである。昨年2月の記事掲載後の調査で、その真の創始者が松代町の山寺信であることがわかった。
ビン口に紙を巻きつけて白化させ、高品質のキノコを生産する現在の栽培法は、昭和12年(1937)に山寺が特許を取得していて、彼の創始であることは間違いない。通説の旧制屋代中学教諭長谷川五作は既成の人工栽培法の紹介者ではあるが、
現在全国に普及している白化ビン栽培の始祖とするには無理がある。山寺については、いずれ詳述したいと思っているが、ここでも訂正しておきたい。
農業は今、冬の季節にあるが、すぐ近くまで春がきていることは間違いない。そしてその春を呼び寄せのは、技術革新、わけても農家の手になる技術革新であることを、歴史は教えてくれている。
|